第2章上顎洞底挙上術をともなうインプラント治療
こんにちは!まるもこです。
前回に引き続き、【正しい臨床決断をするためのエビデンス・ベースト・インプラントロジー】小田師巳/園山亘著の第2章の要約です!
インプラントの治療の一部ににかかわる者として、先生たちがどんなことを考えているのか少しでも知らなければなりませんね。
ということで今回もより理解を深めていく機会にしていきたいです。
※ブログに書いていくことで、自分の中でのアウトプットを目的にしています。
※エビデンスの文献にかかわる部分の記載はありません。
上顎洞底挙上術をともなうインプラント治療
第2章では、上顎臼歯部におけるインプラント治療で必要となる
上顎洞底挙上術(サイナスリフトおよびソケットリフト)の手法、
選択基準,合併症対策についてエビデンスを基に解説しています。
※研究結果と、私の要約では辻褄があっていない部分が多々あります。この本の基盤となっているエビデンスの研究、引用文献等はこの本にしっかり記載されており、詳細が気になる方はぜひ以下のリンクから購入してみてください
上顎洞底挙上術をした部位におけるインプラントの生存率
上顎洞底挙上術は、骨高径が不足する上顎臼歯部で行われる手術で、ラテラルアプローチとクレスタルアプローチの2種類がある。
ラテラルアプローチ(サイナスリフト)は既存骨が高さがほとんどない場合、さらに横幅の骨も不足している場合に行われる。
側壁をを開窓し、上顎洞粘膜を直接的に剥離した後、骨補填材を填入する術式である。
クレスタルアプローチ(ソケットリフト)は骨の高さが不足している場合に行われる。
歯槽頂から窩洞を形成し、上顎洞粘膜に達した後は、骨補填材を介して上顎洞粘膜を間接的に剥離・挙上していく術式である。
手術選択は、患者の骨状態や治療目標に応じて決定される。
上顎洞底挙上術と同時インプラント埋入ができる既存骨高径
・既存骨高径が4mm以上あればソケットリフトでもサイナスリフトも、同時インプラント埋入が可能である。
・既存骨高径が3~4mmの場合は、術者の十分な経験と十分な初期固定が得られるような外科術式やインプラントシステムを採用したうえであれば、同時埋入を選択してもよいと考えられる。
・既存骨高径が3㎜以下の場合や2㎜未満の場合、同時埋入ではなく、待時埋入が推奨される。
上顎洞底挙上術と同時にインプラントを埋入する場合、既存の骨高径が重要な指標となっており、既存骨高径が4~6mm以上であれば、インプラントの初期固定が得られやすく、同時埋入が可能とされている。 骨高径が確保されている場合、治療期間を大幅に短縮でき、患者の負担も軽減されるというメリットがある。
研究によれば、骨高径が少なくとも4mm以上ある場合、インプラントの同時埋入による生存率は非常に高く、約96~98%の成功率が報告されている。
一方で、3mm未満の骨高径では、待時埋入を選択した方が予後が良好ということを示すデータや既存骨高径がこれよりも少ない2mm程度の場合に、初期固定が得られず生存率が優位に低迷するという報告がある。
骨補填材の選択
骨補填材は、上顎洞底挙上術やその他のインプラント治療で不足している骨を補うために使用される重要な材料です。 主に上顎洞挙上では、自家骨、人工骨を用いる。それぞれの骨補填材には特性があり、患者の状態や治療計画に応じて適切な選択が求められる。
- 自家骨: 患者自身の骨を使用。骨形成能力が最も高いが、採取部位の負担が課題。
- 人工骨: 合成材料(例: β-TCP)。感染リスクが低く、骨の足場として機能。
自家骨の使用は治癒期間の短縮が期待されるが、代替材がしばしば単独あるいは併用して用いられる。この代替材の使用はインプラントの生存率に影響しないことが報告されている。
一方で、サイナスリフト・ソケットリフトにおいて、骨補填材を使用せず、埋入したインプラントを支柱として上顎洞粘膜を挙上し、形成したスペースを血餅で満たすだけで骨形成が進行し、良好に推移したケースのインプラントの生存率が骨補填材を使用した場合と同等だったという報告が多数ある。
このことから、骨補填材に関しては、使用の有無から種類の選択において他に勝るベストな選択肢というものはなく、術者の優先事項や経験に選択をゆだねるものとなる。
挙上中に上顎洞粘膜の穿孔を起こした場合は、骨補填材が上顎洞内に漏れだすことを想定して、自然孔(直径3~4mm)を通り鼻から排出されやすいように、細かな顆粒の骨補填材を選択している。筆者らは細粒のβ―TCP(β-リン酸三カルシウム)を用いているが、選択理由はBio―Oss(骨伝導性に優れた天然のウシ由来多孔性骨補填剤)より顆粒が小さいからである。
顎洞粘膜穿孔への対応とその予後
上顎洞粘膜の穿孔は、サイナスリフトにおいて最も高い頻度で生じる併発症で、平均で約20%で起こると報告されている。
しかし、たとえ上顎洞粘膜の穿孔を起こしたとしても、穿孔部を適切に封鎖した後にインプラントを埋入すれば、インプラントの生存率に大きな影響はないとされている。
小さな穿孔に対しては、穿孔部周囲の剥離を進め、穿孔部周囲に正常粘膜を確保した後に吸収性メンブレンを設置して対応することが多い
10mmを超えるような大きな穿孔に対しては、ブロック骨を用いて穿孔部を封鎖する方法もあるが、10mmを超える大きな穿孔部の封鎖と同時に埋入したインプラントの生存率は、小さな穿孔の場合と比べて有意に低い。よって、10mm以上の大きな穿孔を起こした場合は手術を中止するか、サイナスリフトを続行するにしてもインプラントの同時埋入は避けたほうが良いと考えられる。
サイナスリフト後の待時期間
既存骨量の多寡、骨補填材の使用の有無、骨補填材を使う場合は何を使うのかなど、埋入に関する条件が多く、待時期間の明 確な指標は示されていない。
既存骨量に大きく依存するため待時期間は画一的に決められるものではない
目的はインプラントのインテグレーション獲得とその維持である。
サイナスリフトの場合、既存骨が一定以上あることから、理論的には待時期間は9ヵ月よりも短くて良いと考えるが、骨補填材の骨化度 という観点から9か月以降には骨補填材の骨化度が高まるという報告もあり、インテグレーション獲得と維持は既存骨量に大きく依存するといえる。
筆者らの日常臨床では、6ヵ月の待時期間後にインプラントを埋入している。
6か月後の埋入時にインテグレーションが不十分であったとしても、そのさらに2~3ヵ月間、インプラントがインテグレーションする時間を待てば、その間も填入したBio―Ossの骨化も進むと考えているため、Bio―Ossを単独で骨補填材として用いた場合でも6ヵ月の待時期間後にインプラントを埋入している。
筆者らの研究においても、上記と同様のケースでは既存骨埋入と差は認められなかった。
ただし、待時期間を短縮するうえでは荷重開始時期、最終上部構造作製時期などを判断するため、ISQ値の測定をしながら進めていくことを強く推奨する。
インプラント長径の選択
筆者らは上顎洞底挙上術をした場合でも8mmのインプラント長径を第一選択にしている
既存骨埋入におけるインプラントの標準長径は8mmであると1章のインプラントの長径で詳述した。上顎洞底挙上術を行った部位における長径8mmのインプラントの生存率も、既存骨における生存率と差がないことが報告されており、その良好な予後を確認している
歯冠‐インプラント比について
筆者らは、2:1程度の歯冠―インプラント比であれば臨床上、十分に許容できると考えている
上顎洞底挙上術が必要になるような上顎自歯部において8mmを選択すると、臨床的な歯冠―インプラント比が悪くなることが多い。
歯冠―インプラント比に関しては、辺縁骨吸収量、機械的・生物学的合併症には相関がないこと、生存率にも影響を及ぼさないことが示されている。
しかし、歯冠―インプラント比が3:1を超えるような極端な例では生存率や骨吸収との関連も示唆されているという報告もある。
ソケットリフトの選択基準
既存骨高径が4mmあれば長径8mmのインプラントを用いたソケットリフトを第一選択にしている。
ソケットリフトは、サイナスリフトに比べて患者への外科般的に待時期間も短いが、注意点が多々ある。 盲目的な処置であるため、術中にCT撮影を行い、上顎洞粘膜の穿孔の有無や、上顎洞粘膜の挙上量を確認しながら注意深く手術を進めていく必要がある。
また、穿孔させてしまった場合や、サイナスリフト併用での開洞予定部位に太い後上歯槽動脈が走行している場合、など別のアプローチが必要になることも多く、様々な視点からの審査が必要である。
ソケットリフトでの上顎洞粘膜の限界
臨床上は6mm程度の上顎洞粘膜の挙上が十分可能である。
ソケットリフトで実際に骨補填材を填入し、洞粘膜を何mm挙上したら上顎洞粘膜が穿孔するかを評価した報告では、X線で骨補填材の溢出が認められないのは4~5mmの挙上の範囲だと認められた。
一方、X線で骨補填材の溢出を認めるような臨床的にも失敗と考えられるような大きな穿孔は、上顎洞粘膜を6mm以上挙上してはじめて生じている。
長径6mmのショートインプラントを用いたソケットリフト
長径6mmのインプラントをソケットリフトで用いる場合は、現状では連結が望ましい
既存骨の高さが4~6mmの部位に対して、長径6mmのインプラントをソケットリフトで埋入した経過が報告されているが、単独植立にもかかわらず、既存骨埋入と比較しても遜色ない成功率が示されている。
一方で、ソケットリフト併用の長径6mmのインプラントの生存率は低いという報告もされている。
長径6mmのインプラントの単独植立の可否については現在のところコンセンサスが得られておらず、機能回復に至るエビデンスは弱い。
耳鼻咽喉科医との連携
上顎洞内が炎症性軟組織の陰影で充満しているような場合、耳鼻咽喉科医との連携が必須である。
術前のCT検査において、炎症性軟組織の陰影で充満している場合、自然口が閉塞している可能性がある。
そのような場合、自然孔を開塞させている病変を除去し自然口を開大させる必要があり、鼻内に内視鏡を挿入して行う内視鏡下鼻内副鼻腔手術(ESS:Endoscopic Sinus Surgery)が一般的に行われている。 自然孔が開大すれば、上顎洞は正常化され、インプラント治療を進めることができる。
症例 1:サイナスリフトにおける上顎洞粘膜穿孔時の対応と穿孔の有無が増生結果に及ぼす影響
歯根が上顎洞底を押し上げるような位置にあるため(クラス4)、抜歯後、上顎洞底は平坦化、下方拡大しインプラント埋入時に十分な初期固定を得られる骨高径は残らないと予想された。
通常、4~6mm以上の骨があれば初期固定を得やすく、成功率が高まるが、抜歯後の骨量は2㎜程度と予測されるため、。
両側にサイナスリフトを行い待時期間をおいたのち、埋入するという治療計画を立てた。
機能回復は6番までの短縮歯列にする予定にした。
抜歯後 2ヵ月の術前CT画像では、両側ともに上顎洞粘膜はほぼ正常で、予測した通り、既存の骨高径は2mm以下であった。
サイナスリフト
静脈内鎮静下で左右両側に同時サイナスリフトを行った。右側ではBio―Oss(骨伝導性に優れた天然のウシ由来多孔性骨補填剤)、
左側は術中に洞粘膜の穿孔を起こしたため、穿孔部をBio―Gide(吸収性メンブレン)で修復し、骨補填材はCERASORB(M高純度のβ-リン酸三カルシウム(β-TCP))を用いた。
ここでは口蓋側までしっかりと洞粘膜を剥離し(図中青矢印)、増骨と既存骨の接触面積を広く確保することが重要である。
6か月後
6か月間、増骨を待ち、長径8mmのティッシュレベルインプラントを埋入。右側は通常埋入、左側は右側に比べて獲得できた増生量 が少なく、ソケットリフトを併用してインプラントを埋入した。3カ月後にインテグレーション獲得を確認し、最終補綴装置作製を行った。予後
増生部位や辺縁骨は安定し、臨床症状もなく、経過は良好である。
まとめ・感想
上顎洞底挙上術はサイナスリフト(側壁から)ソケットリフト(歯槽頂から)の2つがあり、両方とも非常に確立された硬組織増生術だということがわかりました。
しかし、穿孔のリスクやそれに対する適切なアプローチがインプラントの生存率、患者さんの満足度にも大きく影響するため、やはり術前の審査診断、術中のCTやX線の確認など、慎重に進める必要があるということがわかりました。
歯科技工士としては主に3Dガイド製作の部分で大いにかかわる内容です。
先生がどんな診断をして、どんな治療計画を立てるのか、そしてそれに対応したガイドを製作するために非常に参考になる内容だったと思います。
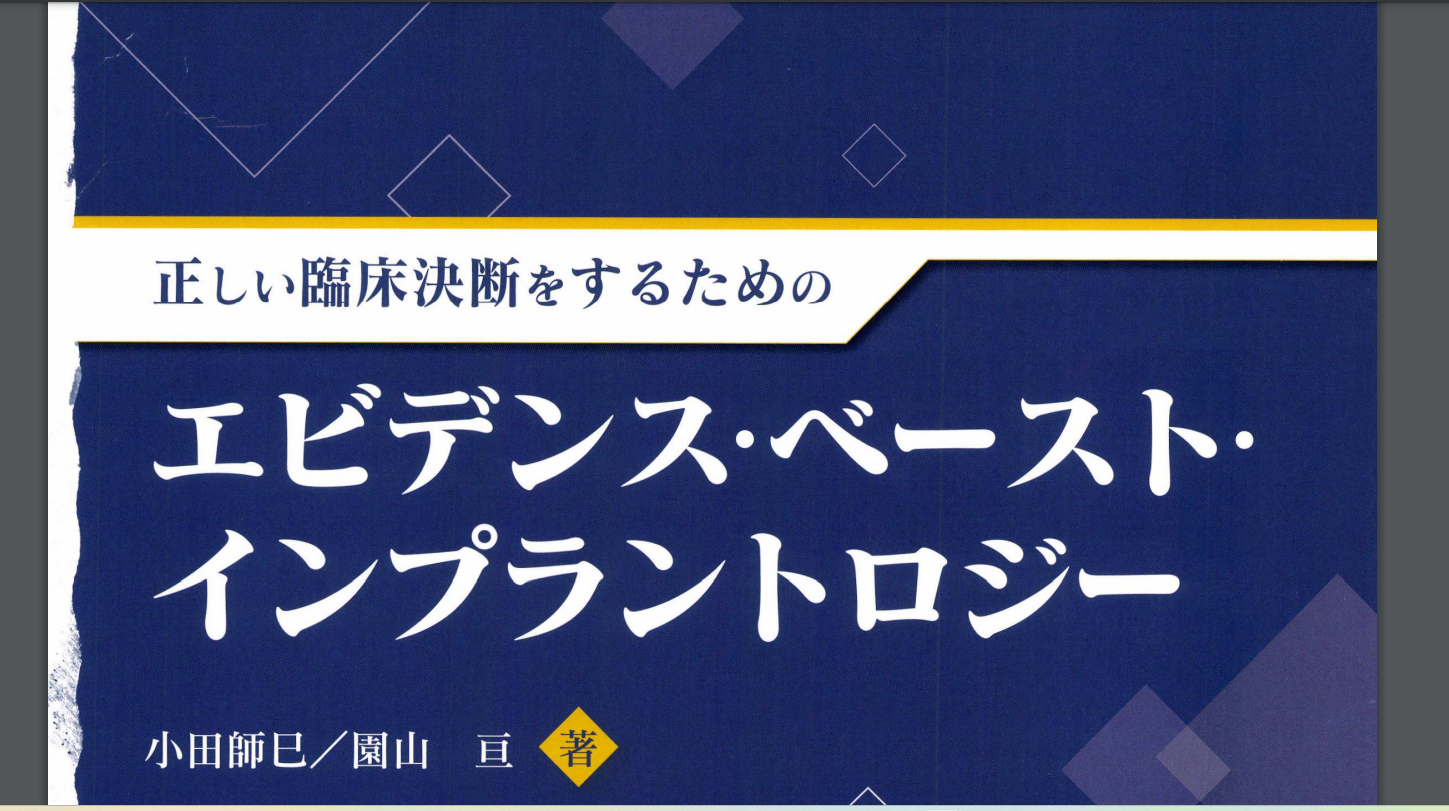


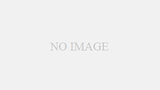
コメント